10月21日はあかりの日!プロが教える照明・スイッチのお掃除術

こんにちは!
ハウスクリーニング歴20年のコラム担当スタッフです。
皆さんは今月「10月21日が“あかりの日”」だとご存じでしたか?
この日は、エジソンが白熱電球を完成させたことを記念して制定された日。
明かりの大切さを改めて感じ、暮らしの“灯り”を見つめ直すきっかけにしてほしい──そんな想いが込められています。
ところで、照明器具やスイッチの掃除、最後にしたのはいつでしょう?
毎日使っているのに、意外と“忘れがちな場所”なんですよね。
でも実は、照明のホコリやスイッチの皮脂汚れを落とすだけで、部屋の明るさや清潔感が驚くほど変わります。
今回はこの「あかりの日」に合わせて、プロの目線から照明器具・スイッチまわりの正しいお掃除方法をじっくりご紹介します。
やり方ひとつで、安全に・効率よく・そして気持ちよくピカピカになりますよ!是非参考にしていただければ幸いです。
10月21日は「あかりの日」──照明を磨いて暮らしを明るく
10月21日の「あかりの日」は、数多ある記念日の中でも特別です。
“明かりがあるからこそ、私たちは安心して暮らせる”のですから、感謝してお掃除を行いたいものですね。
まずはあかりの日のその由来や背景、そして「照明掃除がもたらす心の明るさ」についてお話しします。
「あかりの日」ってどんな日?由来と意味を知ろう
1879年10月21日、アメリカの発明家トーマス・エジソンが世界で初めて実用的な白熱電球を完成させました。
それまで夜の街はランプやろうそくの薄明かりが頼り。電気の灯りは人々の暮らしを大きく変えました。
この偉業を記念して、日本では1981年に「日本電気協会」などが中心となり「照明の日」=“あかりの日”を制定。
以来、毎年この日を中心に、明かりの大切さを広めるイベントが各地で行われています。
照明は、単に部屋を照らすための道具ではありません。
家族が集まるリビングの灯り、勉強机のランプ、玄関の照明──どれも暮らしの安心や温かさを支えてくれる“影の主役”です。
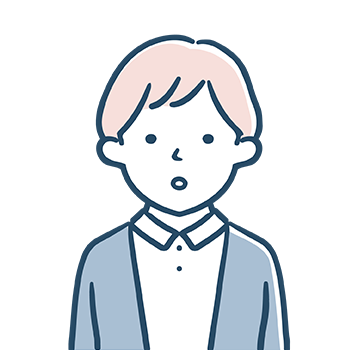
普段当たり前に使っているけれど、無いことが考えられませんよね。人類史上に残る、ありがたい発明と思います。
照明掃除がもたらす“心の明るさ”とは
私が仕事で多くのお宅を訪問してきて感じるのは、照明をきれいにすると気分まで明るくなるということです。
くもったカバーやホコリだらけの電球を掃除したあと、「なんだか部屋が広く見える」「空気まで澄んだ気がする」とお客様が言われます。
光は人の心理に影響を与えます。
明るさが5〜10%上がるだけで、幸福度が高まるという研究もあるほど。
だからこそ、「あかりの日」は単に“電気を大切にする日”ではなく、“暮らしをリセットする日”でもあるんです。
年に一度、部屋中の照明を見直して、ホコリを払いながら感謝する──そんな日として過ごすのも素敵ですね。
なぜ照明は汚れる?ホコリ・油・静電気の意外な関係

照明器具をよく見ると、意外なほどホコリが積もっていたり、カバーの内側がうっすら茶色くなっていたりしませんか?
実は、照明の汚れには“熱”と“静電気”が深く関係しています。
この章では、照明の汚れのメカニズムと、汚れを放置することで起こるトラブルを詳しく見ていきましょう。
天井照明は“ホコリの温床”!熱と静電気のダブル汚れ
天井の高い位置にある照明は、空気中のホコリが最も集まりやすい場所のひとつ。
照明が発する熱によって上昇気流が起こり、ホコリが引き寄せられやすくなります。
さらに、LEDや蛍光灯は点灯中に静電気を帯びやすいため、ホコリがピタッとくっつくんです。
こうして積もったホコリは、時間とともに黒ずみ、光をさえぎってしまいます。
実際にプロの現場で測ると、ホコリで覆われた照明は明るさが約20%も低下していることもあります。
それだけで部屋全体が暗く感じてしまうので、定期的な掃除が必要なのです。
キッチン照明に多い“油膜汚れ”の正体
キッチンの照明器具を外すと、ベタベタした汚れがついていることがあります。
これは、調理中に空気中に舞う油煙(ゆえん)が照明に付着したもの。
油とホコリが混ざり合うと、しつこい“油膜汚れ”になり、きちんとした掃除が必要になります。
特に天井近くの照明やレンジフードの近くは要注意。
この油膜を放置すると、照明の放熱を妨げて寿命を縮める原因にもなります。
お掃除の際は中性洗剤を薄めたぬるま湯を使って、優しく拭き取るのがコツです。
LEDでも汚れる?最新照明の掃除注意点
「LEDだから掃除しなくていい」と思っている方、意外と多いです。
確かにLEDは省エネで長寿命ですが、汚れがつかないわけではありません。
LED照明のカバー部分はプラスチック素材が多く、静電気でホコリを引き寄せやすい特徴があります。
また、内部の電子基盤は水やアルコールに弱いため、濡れすぎた布で拭くのは厳禁。
掃除する際は必ず電源を切り、乾いたマイクロファイバークロスで優しくなでるようにしましょう。
LEDでも半年に1回の掃除を心がけると、光の透明感が長持ちしますよ。
プロが実践!照明・スイッチのお掃除基本ステップ

照明やスイッチの掃除は、正しい順番とちょっとしたコツで仕上がりがまったく変わります。
この章では、私が実際に現場で行っている「安全・効率・仕上がり重視」の掃除手順を、家庭でもできる形にアレンジしてご紹介します。
「照明は高いところにあるから危ない」「スイッチは電気を通していて不安」──そんな心配を感じたことがある方も多いでしょう。
でも、ポイントを押さえれば安心です。
プロの現場でも基本にしている“安全第一でムリをしない掃除”を意識しましょう。

とにかく安全第一を最優先にして作業することが重要です。
掃除前の準備と安全対策──感電・転倒を防ぐ基本
まず大切なのは「電源を切ること」。
感電のリスクを防ぐため、掃除前には必ず照明のスイッチをオフにし、必要に応じてブレーカーも落としておきましょう。
脚立を使う場合は、床が平らで滑らないことを確認。
不安定なイスやテーブルに乗るのは絶対に避けてください。
また、作業中に両手がふさがるため、ポケット付きエプロンや腰袋を使うと便利です。
照明カバーを外すときは、落として割らないよう下にタオルを敷いておくと安心。
安全対策をしっかりしてから作業を始めましょう。
天井照明(シーリングライト)の掃除手順
リビングや寝室などに多い「丸型の天井照明(シーリングライト)」は、ホコリと虫の死骸が溜まりやすい場所です。
1年に1回はカバーを外して掃除するのがおすすめ。
- 電源を切る
- カバーを外し、乾いた布でホコリを落とす
- 中性洗剤を薄めたぬるま湯でカバーを拭く
- 水洗い後はしっかり乾燥(自然乾燥がベスト)
- 本体部分は濡らさず、乾拭きでホコリを取る
※蛍光灯・LEDは外したあと、乾いた布で優しく拭く程度にしましょう。
指紋が残ると発熱の原因になるので、必ずクロスを使うのがポイントです。
ペンダントライト・間接照明の掃除テクニック
ペンダントライトはおしゃれですが、意外とホコリが目立ちやすい場所。
コード部分やシェードの上部は、静電モップやハンディワイパーで優しくホコリを取ります。
間接照明(壁面照射タイプ)は、照射面のホコリやカバーの汚れで明るさが半減します。
照明の反射面には傷がつきやすいので、マイクロファイバークロスの“押し拭き”で。
強くこすらず、軽く押し当てるようにするのがコツです。
電球・LEDカバーの正しい拭き方
電球やLEDカバーは、素材によって扱い方が異なります。
- ガラス製:乾いた柔らかい布で拭く。油膜汚れは薄めた中性洗剤で。
- プラスチック製:静電気が起きやすいので、静電防止スプレーを軽く吹きかけると◎。
注意点は、“取り外したまま電球を濡らさない”こと。
水分が残ったまま点灯すると故障の原因になるため、完全に乾かしてから装着しましょう。
スイッチプレート・リモコン掃除のコツ
照明と同じくらい汚れやすいのが、スイッチやリモコン。
指で触れる回数が多く、皮脂やホコリが蓄積しやすい場所です。
- スイッチプレート:乾いた布でホコリを取り、アルコールスプレーを軽く吹いて拭き取る。
- リモコン:ボタンのすき間は綿棒で。電池を抜いてから作業すると安全。
スイッチの汚れは見落としがちですが、ここをきれいにするだけで部屋全体の印象がパッと明るくなります。
プロの現場でも、仕上げの一手として“スイッチ磨き”は欠かせません。
これに関しては、後半でもう一度詳細に触れさせていただきます。
道具と洗剤の選び方──“磨く”より“拭く”がコツ

照明掃除では、「何を使うか」で仕上がりと安全性が大きく変わります。
ガラス用洗剤や強アルカリ洗剤を使うと、素材を傷めたりくもりの原因になることも。
ここではプロ目線で、家庭でも安全に使える照明掃除アイテムを紹介します。
照明掃除におすすめの道具ベスト5
- マイクロファイバークロス
吸水性・除電性に優れ、照明掃除の必需品。乾拭きと仕上げ拭きの2枚使いがおすすめ。 - 静電モップ(伸縮タイプ)
高所のホコリ取りに便利。天井照明やエアコン上部にも届く。 - 中性洗剤(家庭用でOK)
プラスチックや金属にも安心。原液ではなく、必ずぬるま湯で薄めて使用。 - 柔らかい歯ブラシ・綿棒
スイッチやリモコンのすき間掃除に便利。 - 脚立+滑り止め付き軍手
安全性を高める基本アイテム。作業の安定感が格段に上がります。
これらを揃えておけば、家庭でもプロ並みの仕上がりに近づけます。

無くても掃除はできますが、あるとやっぱり便利ですね。
洗剤は使いすぎ厳禁!中性タイプで十分
照明の素材はデリケート。
特にプラスチックやアクリル製カバーは、強いアルカリ洗剤や研磨剤で拭くとくもり・ひび割れの原因になります。
家庭で使うなら「中性洗剤を水で100倍に薄めたもの」で十分。
また、吹きかけすぎもNG。
スプレーは直接ではなく、布に含ませてから拭くのが鉄則です。
これだけで、カバーやリモコンのボタンまわりのトラブルを防げます。
高所掃除の相棒・静電モップ&脚立の選び方
高い位置にある照明は、無理に手を伸ばすと転倒の危険が。
軽量の伸縮モップを使えば、天井のホコリ取りも安全にできます。
柄の先にクロスを巻き付けるだけで、簡易的なスクイジー代わりにもなります。
脚立を選ぶときは「天板の広いタイプ」がおすすめ。
安定感があり、片手で作業しても安心。
私は自宅用に、持ち運びしやすいアルミ製を使っています。
掃除で変わる!明るさと電気代の意外な関係

照明を掃除すると「部屋が明るくなった」と感じた経験はありませんか?
実はそれ、気のせいではありません。
照明のホコリを落とすだけで、明るさが10〜20%アップすることもあるんです。
この章では、掃除が“光とお財布”に与える意外な効果を豆知識としてお話しします。
照明の明るさは最大20%アップ!ホコリが光を吸収する?
照明のカバーに積もったホコリは、光を反射せず吸収してしまいます。
たった1mmのホコリでも、明るさが15〜20%落ちるという実験結果も。
掃除でホコリを落とせば、同じ電力でも効率的に光が届きます。
つまり、掃除=節電にもつながるということ。
LED照明が増えている今だからこそ、明るさを保つメンテナンスは欠かせません。
LEDもメンテナンス次第で長寿命に
「LEDは10年持つ」と言われていますが、実際は汚れによって寿命が短くなるケースもあります。
ホコリが放熱を妨げると、内部温度が上昇し、チップが劣化してしまうのです。
年に1〜2回、ホコリを落とすだけで寿命を1〜2年延ばせるとも言われています。
また、カバーの汚れを防ぐことで、色ムラやくすみも防止できます。
掃除は“長く使うための投資”とも言えるんですね。
“見えないホコリ”を取ることで気持ちまでスッキリ!
照明を掃除したあと、部屋が明るく見えるだけでなく、気分まで軽くなる感覚は誰しもあると思います。
これは心理的にも実証されていて、「部屋の明るさ=心の明るさ」に通じると言われています。
日々の疲れを感じたときこそ、照明のホコリを落とす。
ほんの10分の作業でも、心がリセットされるはずです。
「あかりの日」にぴったりのセルフケアですね。
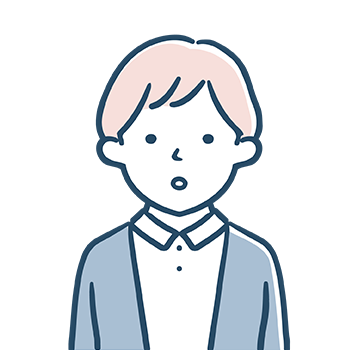
何となく、明るいと安心感がありますよね。
やってはいけない照明掃除──プロが見た失敗例

照明掃除はコツをつかめば簡単ですが、間違ったやり方をすると感電・故障・破損のリスクがあります。
この章では、私が20年間の現場で実際に見てきた「やってはいけない・または注意すべき掃除の例」を紹介します。
どれもついやってしまいがちなことなので、ぜひチェックしておきましょう。
電源を切らずに掃除して感電!?
「スイッチをオフにしたから大丈夫」と思っていても、照明器具には微弱な電流が流れていることがあります。
特にLED照明やリモコン付き照明は、待機電力が常に通電している状態です。
濡れた布で拭いた瞬間に“ピリッ”と感電するケースも珍しくありません。
掃除の前にはブレーカーごとオフにするのも場合によっては有効です。
電源を完全に切ってから作業をすればより安心です。
少しの手間が、大きな事故を防ぎます。
白熱電球の熱に注意!やけどの危険も
昔ながらの白熱電球は、点灯中はもちろん、消灯直後でも非常に高温になっています。
実際、掃除中に「軽く触っただけで指先が赤く腫れた」というやけど事例もあります。
白熱電球の表面温度は、点灯時でおよそ200℃前後にも達します。
見た目では温度が下がったか分からないため、必ず電源を切ってから10分以上冷ますことが大切です。
また、熱を帯びたまま濡れた布で拭くと、ガラスが急冷されて割れるおそれもあります。
白熱球は構造がシンプルな分、扱いを誤るとケガや破損につながります。
「熱が完全に冷めたことを確認してから触る」──これが安全掃除の基本中の基本です。
水拭きしすぎでLED基盤がショートするケース
LED照明の内部には、精密な電子基盤が入っています。
水分が入り込むと、ショートや点灯不良を起こす原因になります。
よくあるのが、「洗剤を吹きかけすぎた」「水でジャブジャブ洗った」というケース。
LED照明は“濡らさない”が鉄則です。
汚れがひどい場合は、布に洗剤を含ませて軽く絞ってから拭くこと。
そのあと必ず乾いた布で仕上げましょう。
カバーを落として破損…やりがちな扱いミス
カバーを外すときに手を滑らせて「パリンッ!」──これ、実は掃除中によく起こります。
特にガラス製のカバーは重く、意外と滑りやすい。
作業前に下にタオルや新聞紙を敷いておくと安心です。
また、カバーを外したまま床に直置きするのもNG。
踏んで割ってしまうこともあります。
必ず安定した場所に置き、乾燥中も倒れないように注意しましょう。
プラスαで差がつく!“照明+スイッチ”同時掃除のすすめ

照明をピカピカにしたら、ぜひ一緒にやってほしいのがスイッチ掃除です。
照明とスイッチはセットで使う場所。
どちらか片方が汚れていると、全体の清潔感が半減してしまいます。
この章では、プロが実践するスイッチまわりのメンテナンス術をご紹介します。
スイッチプレートの手アカ・皮脂汚れはアルコールでOK
スイッチは、家族全員が毎日触る“手の接点”。
特に玄関やトイレのスイッチは、皮脂や手アカが溜まりやすい場所です。
放っておくと黒ずみになり、菌の温床にもなります。
掃除方法はとても簡単。
- 乾いた布でホコリを取る
- アルコールスプレーを吹きかけたクロスで拭く
- 細かいすき間は綿棒で仕上げる
ツヤが戻り、触ったときの感触もサラッと気持ちよくなります。
“壁の明るさ”を取り戻す小さな掃除ですが、実は印象アップ効果は絶大です。
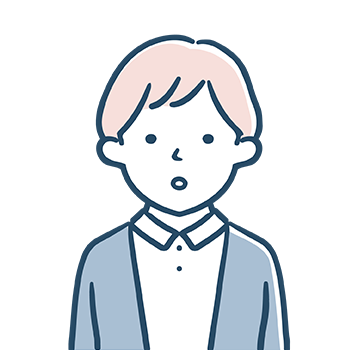
恥ずかしながら、掃除したことが無かったです。人が触るものなのでこれからは衛生的にしたいですね。
エアコン・照明リモコンの掃除と除菌ポイント
リモコンも手アカが付きやすく、見えない菌が多く潜んでいます。
とくに照明のリモコンはソファやベッド近くにあることが多く、ホコリと一緒に皮脂汚れも蓄積します。
アルコールティッシュで全体を拭き、ボタンの間は綿棒で。
電池を抜いてから作業すると安全です。
仕上げに除菌スプレーを軽く一吹きしておくと、衛生的にも安心。
お子さんが触る機会の多いリモコンは、月に1回の掃除を習慣にしましょう。
壁まわりの黒ずみ・手跡を防ぐメンテナンス術
スイッチまわりの壁紙には、黒い手跡ができやすいですよね。
この汚れの原因は、手の皮脂とホコリが混ざった“皮脂膜”。
一度つくと落としにくいので、早めのケアが大切です。
メラミンスポンジを軽く湿らせて優しくトントンと叩くように拭けばOK。
こすりすぎると壁紙の表面が剥がれてしまうので要注意です。
汚れ防止スプレーを仕上げに吹いておくと、再付着を防げます。
まとめ──“あかりの日”におうちをピカピカに
「あかりの日」は、私たちの暮らしに光をもたらしてくれる“灯り”に感謝する日。
電球を発明したエジソンに思いを馳せながら、身近な照明をきれいに整える日でもあります。
照明を磨くことで、部屋が明るくなるだけでなく、心まで前向きになれる──そんな不思議な力があります。
掃除を終えてスイッチを入れた瞬間、「わぁ、明るい!」と思わず声が出る。
この瞬間が、照明掃除の一番の魅力です。
光がよみがえると、部屋の印象も気分も一気に変わります。
まるで気持ちのスイッチまでONになるような感覚です。
家族から「なんか部屋が明るくなったね」と言われたら、それは最高のご褒美ですね。
実際に多くのお客様が、「掃除してから家の雰囲気が明るくなった」と喜ばれます。
照明掃除は、心に光を灯す小さな習慣でもあるのです。
あかりの日をきっかけにお掃除してみませんか
10月21日の「あかりの日」をきっかけに、毎年“照明チェック&お掃除デー”をつくってみませんか?
1年分のホコリを落として、新しい季節を明るく迎える──そんな習慣を家族で持つと、暮らしがより心地よくなります。
照明を磨くことは、暮らしを大切にすること。
スイッチを拭くことは、日常を丁寧に整えること。
ピカピカの灯りの下で過ごす時間は、どんな高級照明よりも温かく感じるはずです。
どうぞ今年の「あかりの日」は、おうちの灯りをじっくり磨いてみてください。
明るさの中に、きっと“小さな幸せ”が見つかりますよ。

